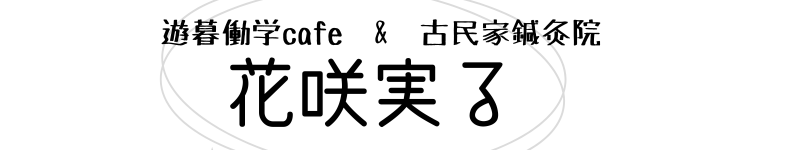安心で楽しく暮らしていくために、個人的な食糧自給率を上げたいという動機で始めた自給農ですが。
どんどん欲深くなって、果樹栽培のお勉強もしてたりします。
故郷・和歌山県の自然農の農業塾で、桃の栽培について学んだ中で、あれ?収穫をふやすためにいろいろと手をかけると、手間がかかるのに、出来たものは安くなってしまい、なんだか苦労ばっかり増えてもしかしてちょっと不幸なのか?という発見があったのでシェアしたいと思います。
和歌山で超低農薬・無肥料の桃栽培をまなぶ
先日は桃の袋掛け作業お勉強してきました。

つぼみのときにつぼみを落とす摘蕾
花が咲いたら花を落とす摘花
小さな実がついたらその実をおとす摘果
と、最終120枚から150枚の葉っぱにつき、1つの桃まで数を減らしていきます。
桃って高いはずです。
恐ろしい手間・桃の袋掛け
そして、そうやって大事に大事に残した、1つ1つの桃の実に袋をかけていく作業。
それが桃の袋掛けです。
袋をかける意味は、主に虫と鳥の害の予防との事でした
ピンポン玉より少し大きいサイズに育った桃に、紙でできた袋をかぶせホッチキスで止めます。


葉を巻き込まないように、実を傷つけないように、落とさないようにと気を使う事は多く、なかなかに繊細な作業。それを1つ1つの実に施していくのです。
もちろん、桃は木の上になっているわけですから、高いところの実には手がとどかないので脚立をつかいます。
1回上って、1個、2個、袋をかけ
「あー、あの一個、もうちょっとで手が届くのに」と精いっぱい手を伸ばしても、届かない。
そうなったら脚立を降りて、動かし、またのぼる。
正直、桃農家の嫁にはなれないと思いました(ちなみになってくれとは言われていない)
ほんと桃って高いはずです(2回目)
二重の袋が生む不自然さと手間
今回実習でかけさせてもらった袋は一重の袋ですが、和歌山で慣行農法をされている農家さんでは一般的に2重の袋を使うそうです。
慣行農法では除草剤を使って草を生やさない
⇩
桃畑の温度が夜になっても下がらない
⇩
2重の袋で光と熱を遮断しておかないと、桃が小さいうちに赤くなってしまう
ということで、商品にならないそうです。
そのため、慣行農法では、2重の袋をかけた後、実が大きくなったころにさらに2重の袋の外側だけをはずして、最後に桃の実に光と熱をあてる、という作業まで入ってくるそうです。
本当に、桃って高いはずです(3回目)
お金をかけて除草剤を撒き、草刈り、
お金をかけて一重の袋よりも高い2重の袋を買い(1重の袋の4倍のお値段らしい)
手間をかけて袋を外す(1重の袋なら収穫の時に袋ごととるのではずす手間はさほどかからない)
しかし、なんと驚くことに、というか、一般の方の多くのイメージ通り。
自然栽培の桃の方がお値段は高くなるそうです。
むーん、お金ってなんでしょうね。
もちろん、慣行農法は肥料をたくさん使うので、1本の木にできる実の数はおおくはなります。
もちろん、そのおかげで私たち消費者の手の届きやすい価格になっている、というわけなので、慣行農法の農家さんにもただただ感謝、なのですが。
でも、昨今、肥料の値上がり、どころか、もう手に入らない、なんて話も聞えてきています。
手間かけて、お金かけて、たくさん作って安く売る。
でもそのやりかたも、もはや持続不可能になりつつある。
もう、むーん、むーん、むーんです。
そしてもう一つ、むーん、ってなった話があります。
手間をかけないとどうなるのか?袋をかけない地域での話
和歌山県では、桃に袋をかける栽培方法が一般的だそうですが、福島県などでは袋をかけない地域もあるとのこと。
「袋をかけなくても鳥や虫に食べられないんですか?」と聞くと、
「みんな袋かけないから、鳥も虫もいろんなとこでちょこちょこ食べるわけ。結局、1軒の農家はそれなりに収穫ができるんですよ」
とのことでした。

…これまた手間をかけて袋をかける意味って何なのかなぁと考えてしまいました。
できるだけ、自然なほうが、結局みんな楽で、それなりに効率よく生きられるんじゃないの?
と思わされた学びでした。
人間も無理しない方が結局効率が良い?
人間もそうで、ホントはみんなのうたの名曲
「朝日と共に起きてきて、夕陽と共にねてしまう」
カメハメハ大王みたいな生活に、みんなでシフト出来たら、楽なんだろうなぁ。
まぁ、それは極端な話だとしても、無理をしてたくさんのお金を稼ごうとしたり、たくさんの評価を得ようとしたりせず、もっとありのままの自分で、安心して、気持ちよく生きられる方法を自分も模索していきたいし、周りの方ともシェアして、みんなで少しずつ楽な生きられる場所をつくっていきたいなぁ、なんて思います。
あ!今回のお話しは、あくまである一つの側面から自然栽培と慣行農法を較べてみた個人的感想で自然栽培の方が楽ちんだよー、なんて口が裂けても言えないことは、最後にしっかりお伝えしておきます。
私ももうちょっと肩の力をぬいて、自分らしくいられる場所がほしいなぁ、と思っている人はお気軽におといあわせくださいねー。