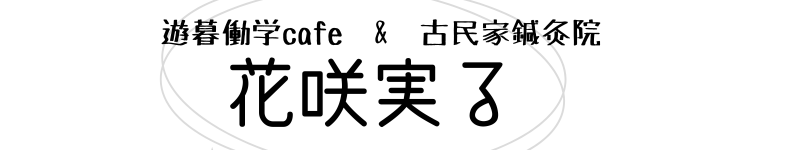オーナーさんの田んぼの稲刈りが終わり、精米もつつがなく完了。
残されるのは大量の「もみがら」

稲の種であるお米をつつんでいた固い殻。有機物だからそのまま土に戻せばいいんじゃないの?とおもっていませんか?
私もそう思っていました。
でも、ダメなんですって!知ってました?
何でも硬すぎて土に還りにくく、分解されにくいせいで、いろいろ問題を起こしちゃうらしいです。
わたし、専門家じゃないので詳しいことはAIさんに聞いちゃいました。結果を下にまとめますね。
もみがらを“そのまま”土に入れてはいけない理由
- 分解に時間がかかりすぎる
もみがらは非常に硬く、自然分解に数年かかることも。畑づくりの妨げになる。 - 分解の途中で窒素を奪ってしまう(窒素飢餓)
微生物がもみがらを分解するときに、土の中の窒素を大量に使うため、植物の生育不良につながる。 - 水はけ・通気性が逆に悪くなることも
土中でかたまりになり、根の伸びを妨げる場合がある。 - 害虫・カビの住処になる可能性
分解しきれていない有機物は、コウモリガ・ナメクジ・カビ類の温床になることも。
なるほどです、これはいれてはいかん!
ではこれをもみがら燻炭にするとどんないいことがあるのでしょう。
これまたAIさんにきいてみました
もみがらを“燻炭(くんたん)”にする利点
- 土をふかふかにする
多孔質で軽く、通気性・排水性がアップ。 - 微生物が住みやすい
小さな穴が多く、土の中の良い微生物のすみかになる。 - 酸性をやわらげる
燻炭には弱アルカリ性の性質があり、土壌改善に役立つ。 - 肥料の保持力が高まる
肥料をつかまえて保持してくれるので、植物が吸収しやすい。 - 環境にやさしい資源循環
捨てずに活かせるエコな素材。
おお、これはめちゃくちゃ良さそうです!だんぜん、燻炭にすべきですね!
でももみがらを燻炭にするっていったいどうするんだ?
と色々調べてみました。
いろいろな燻炭づくりのやり方
プロの農家さんはこのようなものを使われるようです
でも、なんか、あんまりいろいろ買いたくない…。
でさらに検索したところ、100円均一の材料と空き缶を使って作る方法もあるにはあったのですが。
わたし、そんなに器用じゃないんですよね。で、熱を加えるものだし、多分手作りだとすぐにこわれちゃうんじゃないかなぁと。
100均とはいえ、材量を買って、手間かけて作ってすぐ壊れたら癪に障るじゃないですか?
で、思いだしたのが、いつもお世話になってる清阪terraceで聞いた話。
「紙で作った煙突を燃やすだけで、燻炭が作れちゃう」
何千円もする機械の代わりを紙の煙突でできるなんて。
そんなウマイ話があるものか?
あったんです!こちらがその動画!
これ、まじで活気的です。
ということでさっそく私も試してみました。
1回目のチャレンジ・燃え上がる煙突の恐怖に耐えかねる
安全のため、バケツにたっぷりの水を用意し、新聞の太い束で煙突を作り、火種を入れて点火。
すると動画の米袋の煙突のイメージよりも、早々にもうもうと炎が燃え上がり、しかも倒れてしまいました
こ、怖い!
燃え上がる炎の恐怖に耐え兼ね、速攻で消火!
ちーん。
炎に恐怖を感じる、野生動物の気持ちが少しわかった気がしました。
あまりにこわかったので、その日はもうあきらめて、さっさと片づけて終了しました。
もう一度、先達に聞いてみる
しかし大量のもみがらがあります。これを何とか使えるようにしなければ。もったいない!
ということで、動画を提供してくれている清阪terraceの横峯さんに改めて聞いてみました。
「煙突が燃え上がってこわいんですけど」
「煙突は燃えるもんです」
シンプルな回答。確かに。動画でも煙突燃えてたしね。
ということで、煙突は燃えるもの、と覚悟を決めてリベンジすることに。
2回目のチャレンジ・恐怖の先にみえた一筋の光!
再びバケツにたっぷりの水を用意し、周辺にも水をまき、万全に消火体制を整えてから、新聞で煙突を作り、点火!
やはりもうもうと燃え上がる炎。
ひー!やっぱりこえー!
でも大丈夫。対策はしっかりしてある。ちょっとやそっとじゃ燃え移らない!
煙突は燃えるもんなんだ!
教えてもらった言葉を信じ、自分にいい聞かせて煙突がある程度燃えるのを待ちます。
そして、やっぱり倒れる煙突。ぎゃあ、怖い!
なんでだ!
そりゃ、立て方がまずいんだな。
そんなところは妙に冷静に分析。
そうやって、すこし待ってみると煙突の燃え方が少しおだやかになりました。
お、もしかしてこれならいけるか?
様子を見ながら、煙突の上にすこしもみがらをかけてみました。
するとさらに小さくなる炎。
お、もしかして、こうやって少しずつ山にしていけば、いけるんじゃ?
一筋の希望の光が見えた瞬間でした。
そこから少しずつ、もみがらを燃える煙突の上に置いていきます。
すると炎はやがて消え、白い煙が上がるように。
見ると横倒しになった煙突のすき間からわずかに空気が抜けているのが分かり、おかげで火が完全に消えることなく、炭化がすすんでいるようでした。
これはかなりいい感じ!
そこからは少しずつ、もみがらを足し、黒くなってきたらまたもみがらを足す、ということを繰り返していきました。


出来栄えはいかに
そうやって、別の作業をしながら、見守りつつ数時間が経過。
最終的に、きれいな燻炭ができあがりました!

やったー、ばんざーい!
これで大量にある、そのままではちょっと使いづらい「もみがら」をとっても有益な「もみがら燻炭」に作り換えることができるようになりました!
といってもまだまだ、煙突の立て方や、籾を足すタイミングなどが微妙に難しく、マスターした、とまでは言えませんが、そのちょっと難しいところがまた楽しくて、すっかり燻炭づくりにはまっています。
先日はアルミホイルにくるんだサツマイモを入れて、ついで焼きしてみたら、美味しい焼き芋ができました。
自分の手で、役に立つものを作れるって、なんかうれしいですよねー。
注意点
そんな楽しいもみがら燻炭作りですが、どこでもやっていい、というわけではありません。
防火対策を十分にするのはもちろんですが、お住いの周辺の環境を確認してから行ってくださいね。
特に周辺に畑などがない住宅地で煙が上がると、それだけど大騒ぎになりますので、くれぐれもご注意位くださいませ。