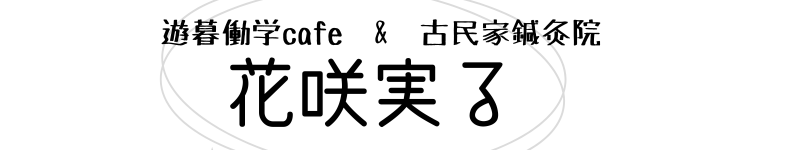色々アクシデントに見舞われつつも、無事に田植えできるサイズまでの育った稲たち。前回の記事はこちら。
今回は、いよいよ田植え、私がどうやって田んぼを作ったか、というお話をシェアします。
お米作りをしたい!というニーズは高まっている気がしていますが、自分には無理、と思っている人がほとんどではないでしょうか?
この記事が「無理!」のハードルを少しでもさげられたらいいなと思います。
今回作るミニ田んぼは、古民家のオーナーさんがお米を育てている田んぼの、一画。小さな三角形の空き地で一面草におおわれたただの原っぱでした。
では具体的にどうやって田んぼにしていったかをご紹介
田んぼにするエリアを決めて、溝を掘る
とにもかくにも田んぼにする場所を決めなければいけません。ということで、この土地の中から田んぼにするエリアをまずはっきりさせるために周辺に溝を掘ってみました。通り道になる畔を残し、三角ショベルで溝を掘っていきます。ただひたすらに掘っては土を上げ掘っては土を上げ。
一人でで小一時間ほどかかったでしょうか。(ちょっと前のことなので忘れてしまいました)出来上がってみるとなかなかきれいな三角形ができていました。

ちょっと満足。こうやって自分のやったことが確実に形になって現れるのが農作業の魅力だなぁといつも思う瞬間です。
あとはこのエリア内の草を短く刈り取り、次は耕運です!
田んぼにするエリアの土を耕す
次に、この三角形の中の土をたがやし細かく砕いていきます。ここも手作業でやりましたと言いたいところですが、ちょっとばかし文明の利器を借りました。
オーナーさんが持っている手押しのエンジン式耕運機。

耕運機の詳しい使い方については、後日動画でもあげようかなと思いますので割愛しますが、普通の車とは違う、いろいろな操作が必要です。
まずはその手順の指導をうけ、そして田んぼまで移動。
田んぼまでの移動は普通に道路をおしていきます。ある程度自走してくれるとはいえ、まぁまぁの重たさなの手押し車をコントロールするのだけでも、なかなかコツが必要です。
そしていよいよ耕運開始。
どこどこどこと勢いよく歯車が回り草刈りをした土を耕してくれます。
慣れぬ機械にトラブル続出
これはすぐ終わりそうだと思った矢先、突然止まる耕運機。
見ると、土を搔きまわしてくれる歯車の中に草がいっぱい詰まって回らなくなっていました。
「げー、草を刈っただけじゃあかんかったんかー!」
そこで一旦エンジンを止め、鎌を使って手で詰まった草を取り出す作業。
その後刈った草を全部退けて再度耕し始めたものの、再び止まる耕運機。
「えー、こんどは何!?」とげんなり。
歯車にはそんなに草はつまっていません。
なんだかんだやっているうちに動き出したのですが、また止まるかもしれないと思いふと目についた。逆回転と言うボタンをおしてみました。
歯の回転が耕運機の進む方向と逆に回る設定との事でしたが、何がどう違うのかわからないけれど、今度は止まることなくドコドコ、ガスガスと順調に進んでいきました。
よっしゃー!と今度こそ機嫌よく耕運を開始。
いかんせん重たい機械を三角形の平坦ではない土地の中で動かすのは大変ではありましたが、なんとかへっぴり腰でがんばりました。

そして何とか無事終了。あとはいよいよ水をいれるだけ!
しかし、水を張るまでの間に時間があいてしまったことで、再び雑草がおいしげり、この過程をもう一度やらなければいけなかったのは、私の計画のミスです。でも2回目の耕運機の使い方は、結構なれたものになっていして、やっぱり何事も練習だなぁと思いました。
田んぼへの給水方法は?
さていよいよ、田んぼに水をいれていきます。私の使わせてもらっている田んぼはオーナーさんの田んぼのすぐ隣。でも最初はオーナーさんの田んぼとはつながっていなかったので、まずそこに溝をある程度ほっておきます。

それから横の水路からもホースで給水。

サイフォン方式、といって水面の高低差を利用した給水方法にチャレンジ。
やり方
①ホースの中を水でみたし、給水側を水の中に入れたまま、排水側にペタッと手で蓋をする
②排水側から空気が入らないように慎重に、かつ素早く、排水側を給水している水面よりも下におろしてから蓋をはずす
なんか、むかし化学か物理かなんかでやったこの理論。
実生活でこんなに役立つとは思いませんでした。
しかし理論はわかっても実際やるのはなかなか難しい。
何度チャレンジしても、なかなか排水側から水が連続して流れ出してくることはなく、ちょろっと出ては止まってしまうを繰り返し。
オーナーさんにコツをうかがったら、
①とにかくしっかりホースを水で満たして
②しっかり蓋をして、
③しっかり下までおろす
あとはできると信じてできるまでやる。
な、なるほどです。
というわけで、できるまでやりました。
で、できました!
何故か水がたまらない
やれやれ、と一安心して帰ったものの、次の日来てみると全然水がたまっていない!
なんでー!?
とおもってみててみたら、ホースからの水がとまってしまっていました。
よく見るとホースの給水側の位置がきのうとはかわっていました。
雨が降って水路の水流がふえ、勢いでホースが動いてしまった時に空気がはいってとまってしまったのかもしれません。
というわけで、またホースをしっかり水でみたして…からやり直しです。
その日は独りで作業。
励ましてくれる人、アドバイスをくれる人、協力してくれる人はいません。
とにかくホース全体が水路に浸かるように、手足、その辺のブロックをつかって沈め、空気が抜けるようにして、排水側を手のひらでピタッとふさぎ、畔を丁寧かつ迅速に下り、排水側を解放!
でも、水が出ない!
それをトータル15回程くり返し、やっと、やっと、
で、でたー!
なんだか感動ひとしおでした。
そしてまた次の日。
まだ水が溜まってない!

こんどはホースからの給水はちゃんとできていました!オーナーさんの田んぼからの水も入ってきている。でも水は一部にしか溜まっていません。
なぜだ!
いれても入れてもたまらない、ということは、考えられるのは水漏れ、です。
高いところから低いところへ流れた後、更に低いどこかに漏れていっているわけです。
うーん、これはどうしたものか。
とても大切な作業をやってなかったことに気づく
そこでふと思い出したのが、参加している手作業で米作りをしているサークルでやった作業。
あのときは水が入った田んぼの土を、スコップで掘り起こし踏み踏みすしていました。これは「しろかき」のかわりだよーってあの時話してたなぁ
ちなみにしろかきとはなにか、こちらの説明をご紹介
代掻き(しろかき)は、田起こしが完了した田んぼに水を張って、土をさらに細かく砕き、丁寧にかき混ぜて、土の表面を平らにする作業です。代掻きには次のような目的・効果があります。
1. 田んぼの水漏れを防ぐ。
2. 土の表面を均して、苗がムラなく生育するようにする。
3. 苗を植えやすくし、苗の活着と発育を良くする。
4. 元肥(もとごえ)をムラなく混ぜ込む。
5. 藁や雑草を埋め込む。
6. 雑草の種を深く埋め込むことにより、雑草の発芽を抑える。
7. 有害ガスを抜き、有機物の腐熟を促進する。
https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/rice/planting/ploughing_01.html
これ見てもわかるように
1,水漏れをふせぐ!
そうだ!やっぱりしろかきしなきゃいけないんだ!
ということでやることがわかれば後はやるだけです。
ひたすらスコップで土を起こし、足でふみ、をくりかえします。
この作業は独りでやるとなかなかに果てない。
2時間ほどやって、いい加減日も暮れてきたので、その日はいったん切り上げました。
そしてまた翌日。
案の定、まだ水は半分くらいしかたまっていません。
でも昨日よりはたまっています!
そしてその日はなにより頼もしい助っ人がいます!
それがわたしのおねえちゃん!ちなみに姉も鍼灸師です。

ということで、2人揃って、鍼灸師のアラフィフ鍼灸姉妹が、スコップもって掘り起こし、おこした土を踏み踏み。
当然ですが、土を掘って水の通り道をつけてやると、そこに水が流れてきて、その部分に水が満たされていきます。そして、硬くしまっていた土を掘り起こしふみふみすることで、だんだんと全体がなめらかな泥状になっていき、田んぼに水が引き渡っていきます。
ちょっと話はそれますが、農作業をやっていると、いつも鍼灸治療とリンクする部分が多くて面白いなぁと思います。と言うのも鍼灸治療と言うのは、鍼で身体の中にできた凝り固まった部分をほぐし、そこに血の流れを通すことで、体全体の巡りを良くして健康を保つすると言うことを目的としているからです。
2人で2時間、姉が帰ってからも、1人で1時間ほど作業した結果、ようやく三角の田んぼ全体に水が行き渡りました。これで水が抜けなければ、無事田んぼの完成です!
やったー!!!

まとめ
かなり苦戦はしましたが、なんとかアラフィフ女子にも一から田んぼづくり、できました。もちろん、耕作放棄地からやるような大変な作業ではありませんでしたが、基本は耕して水を入れる、ということに変わりはないかなと思います。
代掻きはトラクターがないと難しいと思われがちですが、人力でもなんとかなるということもわかりました。また一つ、経験と知恵と、すこしばかりの筋肉も手に入れて、達成感も味わえた楽しい遊暮働学という暮らし方。
メルマガでくわしくお話ししていますので登録も解除もお気軽に!